

平成16年10月31日〜平成16年11月06日
|
秋の陽射しが気持ち良い木曜日・・・・仕事が早く済んだので 3時すぎに 後楽園に寄ってみました。
菊花展が 開催され始めたので 多少期待もしてました。
ところが 菊の花がまだまだ蕾みで 見頃は11月3日すぎとのこと。
でも 気持ちが良いので 後楽園の中をそぞろ歩き・・・・・♪
あっ!! 見つけました☆ 秋色のもみじですーー♪
 ほとんどの、もみじは まだ 緑色なのですが・・・一本だけ 午後の陽だまりで 嬉しそうに 色づいている ちょっとオマセな おしゃれサンがいたのです。
  なんだか 得をした気分になりました〜〜。
そうそう それから園内には 小さな田圃があるのですが、丁度 この日は 金色に実った稲を刈り取る真っ最中だったのですよ。
田植えの時は 早乙女姿の女性が 揃って パフォーマンスして TVでも紹介されるのですが、なんとまぁ 刈り取りは 園の整備のおじさん達・・・・。
 鎌を手に 腰をかがめて話しながらの作業で なんだか 楽しそうでしたよ。
ほんの少しの田ですから あっという間に 稲刈りは済んでしまいました。
後楽園には たくさんの松の木があるのですが、冬支度がすんでました。
前日に 松ノ木の幹に 藁(ワラ)を巻く作業終了したばかりだったのです。
園内の松くん達は みんな こんな感じで 並んでましたよ。
 後楽園名物 松の菰巻きです。
 秋になると このように腹巻状に藁を巻かれて冬を越します。 秋になると このように腹巻状に藁を巻かれて冬を越します。 寒がり なのではありませんヨ
雪もめったに降らない岡山ですから、このワラは 虫よけ なんですね。
冬の間 土から上がってくる害虫が この菰の中に入って冬越しします。
春の声とともに それを取り外して 害虫とともに焼いてしまうのです。
菊花の展示会の様子は また菊の花が満開になったら 出かけてきます。 でも この日は 思いがけず、いくつかの深まる秋を見かけることができて、楽しい公園散策になりました☆
|
|
10月23日〜31日まで開催中の、第17回東京国際映画祭に行ってみました。
ベルリン、カンヌ等に並び、アジアで最大、世界11大国際映画祭のひとつとして公式に認められており1985年、「日本にも国際的な映画祭が誕生」したと大きな話題となった映画祭でしたが、回を追うごとに盛り上がりに欠けるようになり・・・。
そんな東京国際映画祭へチケットを頂いたこともあり、初めて行ってみました。

26日、メイン会場の一つである渋谷東急文化村へ。 街中には、旗や看板があちらこちらに飾られていましたが、雨というお天気も手伝っているのか、映画祭で街が賑わっているという様子はありませんでした。
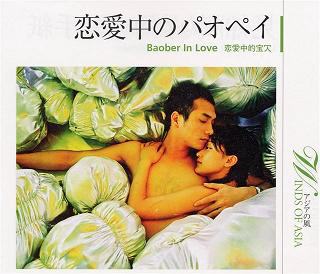
この日は“アジアの風部門”の 「恋愛中のパオペイ」という作品を見てきました。
監督 リー・シャオホン(中国の有名女性監督。国内外の映画祭で多くの受賞歴あり)
作品にもよるのでしょうが、この映画に関しては関係者の来場も少なかった上、映写機の故障で上映開始が1時間も遅れるというハプニングつき。
映画祭で映画を観る、という普段とは違う新たな感覚はここでは味わえませんでした。
29日は、今年から会場になった六本木ヒルズへ。 日比谷線六本木駅改札口を出るとすぐに大きな看板。
ヒルズへと向かう長いエスカレーターを上がっていくと、そこには映画祭の看板と共に多くの出品作のポスターが飾られ、すでに映画祭一色の雰囲気です。
 六本木ヒルズアリーナには特設会場が設けられ、多くの来日ゲストがこの舞台上でイベントを行ったのでしょう。 けやき坂通りにレット・カーペットが敷かれ、華やかにゲストが登場したオープニングイベントでもこちらのステージに立ったそうです。
 渋谷という街とは違い、六本木ヒルズという限定された地区のためか、そこら中映画祭モードいっぱいです。
  当日券、映画祭グッズ売り場。
 おまけ!! 近くのインターナショナル・スクールの子供達でしょうか、先生と一緒に遊びに来ていました。子供達の笑顔が素敵でしょう・・・
 この日は、ソイ・チョンという若い監督の 「愛・作戦」 という香港映画を観ました。
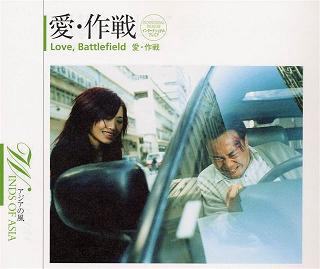 前回とは違い、この映画は海外メディアのPRESS等映画関係者も多く、上映直後には拍手が沸きあがり、監督とのティーチ・インもあったりと、映画祭で映画を観るというのもいいな、と思わせてくれました。
映画上映だけでなく、こちらの六本木会場では様々なマーケットやフォーラムも開催されていて、映画祭のIDを下げた関係者の方々を多く見かけたりと、映画祭を十分に堪能できました。
初めての映画祭体験でしたが、普段映画館で観るのとはまた違った楽しみがあります。
出来れば来年もまた足を運んでみたいと思います。
|
| 7月から4ヶ月過ごした仮住まいの蔵前から大手町に仕事場が変わりました。 蔵前にいる間は大川端(隅田川)の深川・本所・向島の散策ができました。 引越しの日になって鳥越のおかず横丁を思い出しました。  蔵前と御徒町の丁度中間、蔵前通リから1本浅草寄りの細い通リにお惣菜屋さんがならびます。 一寸目についたお漬物屋さんを紹介します。  ・・・というわけで今週は七福神はお休みです。 |
|
江戸時代より”明神さま”と呼ばれ〜親しまれてきた 『神田明神』の祭神は・・・
大国主命(大黒様) 少彦名命(恵比須様) そして 平将門命です。
七福神博士・中野君の縄張りを荒らすつもりは 毛頭有りません!
我が家から 車で秋葉原電気街に行く 通り道に位置しているのです。
江戸開府400年にあたる昨年は 盛大な神田祭が挙行され、平成7年より始まった御造替事業により 社殿他建物が美しく塗り替えられたと聞いています。
それで 久しぶりに 立ち寄ってみたのです。
 「随神門」は ひときわ色鮮やかです!
門をくぐって 境内に入ると 正面に直ぐ社殿が見えます。
商売繁盛・縁結び・勝運祈願・厄除けなどの神様として知られ〜
特に正月には 場所柄 ビジネスマンの初詣客で埋め尽くされます。
折りしも冷たい雨が降っていましたので 参拝者もまばらでした。
帰ろうと思ったその時・・・ 社殿の入り口から 雅楽の調べが聞こえてきました!
それも 近頃テープが多い中 笙や笛の生演奏です♪
・・・ 古式ゆかしい神前結婚式が 執り行われようとしていました!
幸運にも 横の式場から社殿に向かっての 花嫁行列を見ることが出来ました!!
 花婿花嫁は 朱色の唐傘の相合傘でした♪
 お二人の門出に 「雨降って地固まる」の諺を 思い出しました。 お幸せに〜♪
参道を歩いて帰りがけに 鳥居の傍にある 有名な甘酒屋「大野屋」も覗いてみました。
 七五三のお祝いに 家族でお参りにこられたのでしょう。
喫茶室に 7歳の女の子の晴れやかな顔を 垣間見ることが出来ました。
|
|
デルフトからブルージュに移動の途中でロッテルダムに寄りました。
入るや、我が師匠Pieter Bruegel the elderを目指してまっしぐら。
おや?若い学生さん達がブリューゲルを研究中?
美術講座の課題用紙を持って、どんな人が何人描かれているかなどを調査して回っているようです。
答えを記入するたびに笑い転げていました。
 空いたところで記念に まず1枚。
★ Pieter Bruegel the Elder「バベルの塔」1563年〜: 撮影2002年6月13日
 これは池袋で以前お目に掛かった気がします。「バベルの塔」はウイーンにもありますが、サイズはウィーンの作品の縦横はおよそ半分で、塔の建設はこちらのが進み、より高く聳えています。ブリューゲルは実はバベルの塔をもう1枚描いているのだそうですが紛失し、どのようなものかはわからないそうです。
さて、ロッテルダムはHieronymus Boschの出身地ス・ヘルトーヘンボスに近いためかBoschの作品が充実していて楽しみです。
★ Hieronymus Bosch「放蕩息子の帰宅」 1510年頃:
 屋根に穴の開いた怪しい家は白鳥の旗が掲げられており売春宿であることを示してます。それに背を向けて、両親の住む平和な田園の方を目指して放蕩息子は歩いてます。懐からのぞく豚の足は幸福をもたらすお守りで、背負い籠の木の匙は濫費の象徴との事。顔は宿に向いているので、未練があるのでしょうか?この白髪の老齢の男の顔がなんとも味がありますね。
同「部分」放蕩息子の顔  ★ Hieronymus Bosch「聖クリストファー」1504年頃:
 川を渡れずに困っていた少年を背負って渡ると少年はたちまちキリストの姿となって天に昇ったという場面を描いています。クリストファーは「キリストを背負う人」という意味で、欧米ではいまでも旅に出るときこの聖クリストファーの像を刻んだお守りを首にかけて出発する習慣が見られるそうです。
この絵にはいろいろと描き込まれていますが、その意味はなかなか難解のようです。
★ Hieronymus Bosch「カナの結婚」1475-80年:  コリント書の「あなたの主の杯と悪魔の杯とを同時に飲んではならない。主の食卓と悪魔の食卓に同時についてはならない」を主題に描いたそうです。
手前の2匹の犬と、右で甕に水を注ぐ男は後世の加筆だそうです。この水がワインに変る奇跡が起こるのですね。
この人は1人早々と杯で酒を飲んでいるようですが一体何者?ワインを足りなくしてしまう悪魔でしょうか?
同「部分」:
 ★ Hieronymus Bosch「地獄と洪水」:
  このパネルは両面に描かれているので枠に吊り下げられて裏からも見えるように展示されていました。裏は真っ黒で殆ど見えません。
"Sicut erat in diebus Noah"『 ノアの日々そのままであったように』という題の祭壇画両翼と考えられています。
さて、しんがりの大巨匠は・・・・
★ Jan van Eyck「石棺の傍らの3人のマリア」1420年頃:
 この絵はHubert van Eyck作との説もあるようです。
天使がマグダラのマリアと母マリアに「空の墓」がイエス復活の証拠だと告げているところですね。
同「部分」:もう一人のマリアは誰?
 彼の絵はどんなアップにも耐えますね。
|