

平成22年10月17日〜平成22年10月23日
1. Ski Plane in NZ
by 小松 公子さん
|
ニュージーランド人が選んだ 最も☆この国らしい風景とは・・・
 (絵葉書にならないように〜仲の良いご夫婦を拝借。 皆様も フルムーンに訪れては如何ですか?)
ニュージーランド(NZ)での 最初の印象は・・・
”イギリスの田舎の牧草地の風景を更に広大にした〜その背景に スイスの雪山が連なっているよう” でした。
NZの売りは 何といっても豊かな自然! ・・・国土の3分の1以上が 公園や自然保護区になっています。
<国立公園>
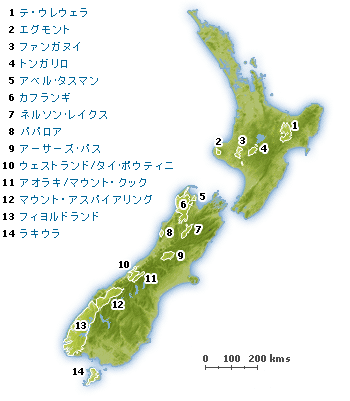 14の国立公園は それぞれ特徴を持っていますが・・・ その中で マオリ(先住民族)の言葉で ”テ・ワヒボウナム”(宝のある場所)と言われている〜 南島・南西部の国立公園 ⑩ ウエストランド ⑪アオラキ/マウント・クック ⑫マウント・アスパオアリング ⑬フィヨルドランド
の4つを含む場所は 『世界自然遺産』にもなっています。
今回は ⑪アオラキ/マウント・クック国立公園 を ご紹介致しましょう。
島の中央に連なる山々は〜 ”南半球のアルプス山脈”と呼ばれる 「サザンアルプス」です。 3000m以上の峰が18有る中で 国内最高峰のMt.クック(3,754m)が その美しい姿を見せています。
マオリ語では ”アオラキ”(雲を貫く)と呼ばれています。
|
|
麓に ミルクを溶かしたような青緑色(ミルキーブルー)に湖面が輝いている☆「テカポ湖」があります。 この色は・・・氷河が削り取った〜山肌の岩石の微粒子が 湖の水に溶け込んだためです。
 |
|
湖畔に佇む☆シェパード教会(写真の真ん中辺)の 祭壇奥の窓から〜〜 湖とサザンアルプスの風景が 1枚の絵のように見えました。
 余談ですが・・・ ”南十字星ウォッチング”は 晴天率が高く 人口光も殆ど無い〜この付近がお勧めです。
 国旗にも 取り入れられている”南十字星”・・・ 国旗にも 取り入れられている”南十字星”・・・ 我々も ホテルから ちょっと歩いて暗い場所を見つけ〜 南半球ならではの 天の川に浮かぶ星座を観察しました。満天の星空♪・・・天の川も とても大きく感じられ〜 流れ星も たくさん見ることができました。
その”星空”で 世界自然遺産に 登録を申請しているようですよ!しかも・・・ 前代未聞のアイデアを出したのが その地で星空ガイドをしている ひとりの日本人というから 面白いでしょう〜!?
さて 本題に入りましょう。 この度のNZツアーで 1番楽しみにしていたことは〜〜 ”スキープレーン”でした。
サザンアルプスを間近に見下ろす遊覧飛行は 天候に左右されるので その時まで心配でした。風が強い日も飛びません。 予備に 次の日も その為に空けていました。前日の予報では 天気が下り坂で 強い南風が近づいてくるようでした・・・。
幸いなことに 天気の崩れは ゆっくりとなり〜予定していた午後は 晴天で無風状態。・・・最高のコンディション!
7人乗りのセスナ機は 軽やかに飛び立ちました。
 目指す☆Mt.クックが 前方に! その手前は テカポ湖でしょうか!?
 遊覧飛行ならではの風景が 我々を楽しませてくれました。  氷河が溶け出した〜銀色の川が 眼下に見えます。  雪山の脇を すれすれに飛んで行くので〜 間近に見える景色に 乗客からは ため息が漏れました。  スキーを履いたセスナ機(スキープレーン)が Mt.クックの氷河の☆万年雪に着陸です!♪  雲ひとつ無い青空♪ 雪が キラキラ輝いていました。  後方も 下の写真の風景で〜 ぐるりと雪の岩肌に囲まれていて 其処は別世界。 ・・・静寂そのもの。万年雪上には 降り立った小型機のスキーの軌跡と 我々の足跡だけが クッキリと付けられています。  風もないせいか〜 地上より 暖かい感じがしました。 興奮冷めやらぬまま あっという間の40分の遊覧は終わり〜 地上に戻りました。
今度は レストランから夕食を頂きながら〜 Mt.クックが夕日に染まっていく☆美しい光景を堪能しました。
  |
| 毎週幼虫や卵ばかりでは嫌われそうなので、今週はきれいな蝶も入れました。ぜひご覧ください。
人様から頂いた幼虫でだけなく、自前調達の幼虫や卵の飼育も先週から始めました。
道端で見つけたアカボシゴマダラの幼虫、庭の榎に産み付けられたアカボシの卵、それとお師匠様から頂いたムラサキツバメシジミの幼虫です。さらに、マテバシイと間違えて採取してきた葉に着いていた謎の卵と幼虫もです(正体が判明しました)。
幼虫がお嫌いな方もおられるようなので、今週はまず美しい蝶と花の写真から掲載しましょう。
ヒメアカタテハとキバナコスモス 撮影2010年10月16日
 ヒメアカタテハとキバナコスモス
 このヒメアカタテハは、アカボシの幼虫を見つけた道端にいたものですが、丁度一週間前に孫たちと舞岡公園に行く時にもこの蝶を見ました。同じ固体かもしれません。
ホトトギスの花
 ルリタテハの食草として、この夏、入手に奔走しました。その後、眼が慣れて道端を見ると、公園や茂みに結構あるものだと分かりました。今ちょうど花の時期です。
近所のタブノキ(マテバシイと間違えた)
 うちから100m程の処に生えているのですが、ムラサキムラサキツバメシジミの食樹、マテバシイと思って採取したのですが間違っていました。道端に生えている木で誰の持ちものか存じませんが、何年か前にこの木で、クワガタムシを大量に捕獲したことがあります(クワガタムシは向かいの家の子に全部あげましたが)。その後木は切られたのですが切り株からまた芽がでてこのような大きさに茂りました。
タブノキ
 ここで若芽を採取したとき、たくさんの卵と幼虫が着いていました(先週の報告→こちら参照(最後の2枚の写真です))。
蛾の幼虫かもしれないとのことで、水を張ったバケツに枝を入れて、門の脇に置いて様子を見ていたのですが、だんだん大きくなってこんな姿になってきました。
謎の幼虫は?
撮影2010年10月13日
 小さいうちはオバQのような”頭でっかち”だったのですが、少しバランスが採れて蝶の幼虫らしくなってきました。頭に黒いトゲが3対、尻に白いトゲが1対あります。インターネットで調べるとアオスジアゲハの幼虫らしいことが分かりました。
アオスジアゲハ?
 とてもかわいいでしょう?
お師匠様にもアオスジアゲハの幼虫と鑑定され、真面目に飼うことにしました。
菊花石の花瓶に入ったタブノキの虫
 処遇を間違えていたと反省し、慌てて花瓶に入れ、新しい若葉を採ってきて追加しました。ちょうどよい花瓶が見つからなかったので、中国の会合のお土産に頂いた菊花石の花瓶を使いました(重くて倒れにくい)これに洗濯ネットを被せてベランダにおいてあります。
ところでアオスジアゲハとはこんな美しい蝶です。羽化が楽しみです。
アオスジアゲハの成虫 撮影2010年8月22日(by
兄弟弟子)
 今朝の幼虫
撮影2010年10月16日
 愛嬌のある顔で眺めていて飽きません。鼻毛を出して行進しているみたいです。
隊列を組むアオスジアゲハ:
 自分がとまる葉は食べずに棲家としているようです。他のを食べに行って、必ず戻って来るようです。 現在十数頭がうちにいますが、アオスジと分かったので、明日兄弟弟子にお裾分けすることになりました。餌も一緒に持参するのでタブノキの枝を取りに行ったらまた枝に3頭いたので連れてきました。(それも明日持っていきます。)
さて一方、庭の榎鉢に産卵されたアカボシの卵は孵化して、小さな幼虫になっていました。今朝4頭が確認でき、体長5〜6mmで体は緑で頭はこげ茶です。
孵化したアカボシゴマダラ その1: 撮影2010年10月16日
 孵化したアカボシゴマダラ その2 撮影2010年10月16日
 全部葉の表の先端に着いていました。
次にムラサキツバメシジミですが・・・
ムラサキツバメシジミ 3号と4号 撮影2010年10月16日
 丸まった枯れ葉の中に蛹が2頭寝ています。もう10日ほど寝ているので羽化は間近?
若いムラサキツバメ 5号 撮影2010年10月16日
 もらわれて来たときは随分小さかったのですが、17mm位になりました。天辺の茎を食べているようですが、若芽が不足しているのでしょうか?
若いムラサキツバメ6号と1号の死骸 撮影2010年10月16日
 6号は今日初めて発見しました。 死んだと思った1号を土の上の葉に転がしておいたのですが、今朝見たら黒くなって完全に死んでいました。よく見るとその下で もぞもぞと葉をかじっている口だけが見えました。そこで葉を持ち上げて見るとこのように、1号の死骸と重なるように葉の裏に若い幼虫が着いていました。
死骸の周辺に沿って葉をかじっていたので、死骸が葉にぶら下がってこのようになっているのです。 6号はもらってきた時、卵だったのか、極小さいかで見過ごしていたようです。
なお、1号と2号は死亡が確認されました(死骸がありました)。
アカボシゴマダラの幼虫 撮影2010年10月16日  こちら幼虫で連れてきたものです。1週間位ずっと同じ葉にとまったままです。少し大きくなった気もしますが、あまり変化はないようです。
さて、この先どうなることでしょうか?幼虫や蛹のまま越冬するものもいるようです。 楽しみです。
|
END