|
製作時期は不明ですが、(多分1940年頃ではないかと思われます。)母親が大切にしていた大理石の置時計があります。重量7.6kg、当時の価格は不明です。
私が小学4年生の頃、その中を覗きたくて、分解し、壊してしまいました。母親が亡くなった後に、妹から、私が壊したため、母親ががっかりしていたと聞かされました。そこで、再び動かそうと、時計屋さんに尋ねましたが、修理は不能。例え、修理が出来たとしても、費用は出来高しだいと言われ、自分で修理に挑戦しました。
修理箇所は、1.ゼンマイ(バネ)の破損・・・

そして、2. 歯車の歯こぼれ・・・

3.振り子の時間調整部品(部品名不明)の破損・・・

そして 4.折損した“時間合わせ用つまみ”・・・の4箇所です。
時間合わせ用つまみは、部品がないため、時計ドライバーを加工して作りました。

時計ドライバーを二つに切って、上の写真の右の部分の頭をカット・・・・
さらに、ドライバーの頭をカット。そして、ツルツルの部分にダイスでねじを切ります。

ネジ切りしたところに、ナットを取り付け、半田で固定します。

最後は、ペンキを塗って、時間合わせ用つまみはかんせい!
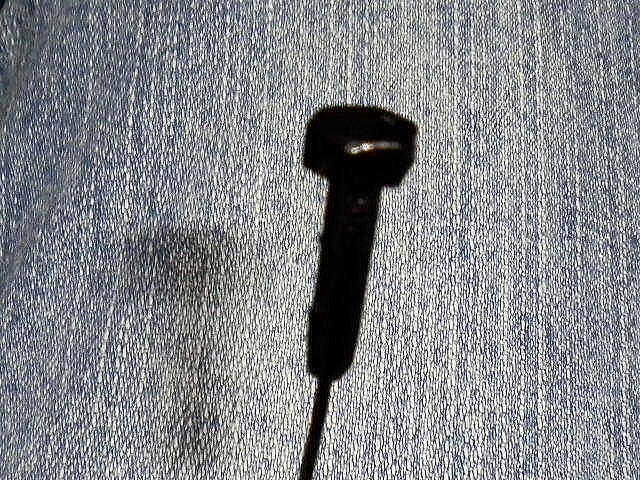
分解して取りだした歯車です。

ゼンマイを緩め、分解した時、完全に緩んでおらず、ビスを外した瞬間にギアが飛び散ってしまいました。
分解したフレームとゼンマイです。

ゼンマイは、巻きつけ部で切れていたので、残った端を曲げ、バーナで加熱し、再度取り付けまました。一枚目の写真は、その加工をした後です。
歯こぼれした歯車の再生加工の状況です。
 歯こぼれした歯形の上に、新しい銅の薄板を張り付け、古い歯車の歯をなぞって、やすりで新しい歯を削りだしました。 歯こぼれした歯形の上に、新しい銅の薄板を張り付け、古い歯車の歯をなぞって、やすりで新しい歯を削りだしました。
修理で困ったのは・・・
老眼のため、現在使用中の遠近両用メガネの上に3.0の老眼鏡を重ね使用したこと、参考資料がないため分解の仕方が分からなかったこと です。
完成した置時計です。 

裏のカバーから出ている“ゼンマイ巻き”と”時間合わせ用つまみ”です。

元の歯型に合わせ、歯車を作るのに約6時間(2枚目の写真の赤い部分良く見ると欠けた歯の下に新たに作った歯が見えます)、振り子の時間調整部品に30分、時間合わせ用つまみの製作に1時間、上手く動かないため、組み立て、分解を3回繰返し、結局、延べ約50時間をかけて完成しました。
時計の遅れは24時間で3分程度。現在約50年ぶりに快調に動いております。
最初は気になり、夜中トイレの時に時計がお休みしていないかドキドキしながら見に行きました。どうやら休まず動いているようです。この時計は6〜7日巻きのようです。
この様な時計の情報をお持ちの方お知らせください。
最後に、皆様のお宅に、昔の時計で動かないのがあったら、ボケ防止に修理に挑戦しますから、遠慮なくお知らせください。但し、動くようになるかは保証できません。(腕時計はだめです)
|

